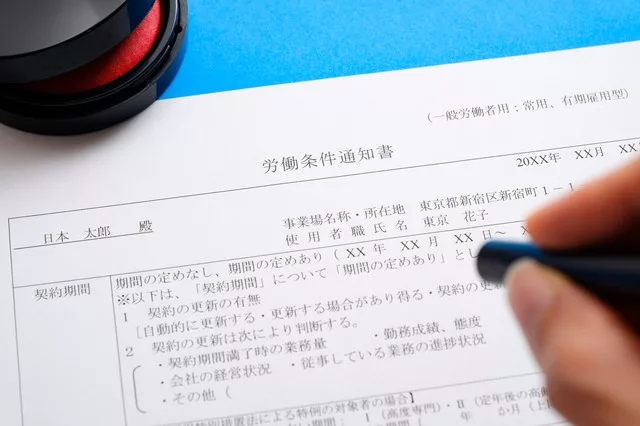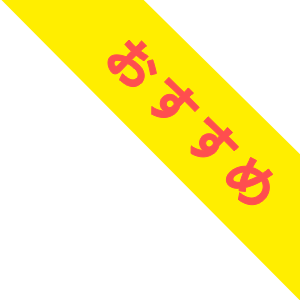目次
契約締結日とは
まず初めに、契約締結日とはどのような日付であったかおさらいいたします。
契約を締結する際には、自社も含めて複数の当事者が存在します。この当事者の間で実際に契約を締結した日付が契約締結日となります。
書面での契約であれば、当事者すべての記名押印や署名捺印が「揃った日」、とも言えます。
では、類似する言葉の「記入日や署名日」と「契約締結日」の違いについても確認してみましょう。
契約締結日と記入日(署名日)の違い
契約書の署名欄には「記入日」であったり「署名日」として、日付を記入する欄が設けてある場合がございます。
この「記入日」や「署名日」は、その言葉のとおり、記名押印や署名捺印を行った日付であって、厳密には、「契約締結日」とは異なります。
例えば、契約書は信書便法により郵送などの手段で送る必要がございますが、郵送した日と先方に届いた日、届いてから記名した日、そして返送された日と、書類の郵送のやり取りの間で時間の経過を考慮する必要があるからです。
契約締結日を定める方法は複数ある

以前のコラムでもご紹介しましたが、「契約締結日」の決め方は想定される方法がいくつかございます。
どのような決め方があるのか改めてご紹介させていただきます。
方法①契約期間の初日とする
まず一つ目の方法は「契約期間の初日」を契約締結日とする方法です。
例えば、契約書には有効期間の条項が設けられており契約の始期を定めている場合が多くございます。
この始期(契約期間の初日)を契約締結日とする方法となります。
この方法であれば、契約における権利や義務の履行機関と揃う形となりますので、採用する企業様やケースは多いかと思います。
契約締結日の決め方としては、相手方の理解も得られやすく採用されやすい方法となります。
方法②最初の当事者が契約書へ署名した日とする
方法の2番目は、最初の当事者が契約書へ署名した日付を契約締結日とする場合です。
例えば、先に契約書へ署名捺印した当事者側で、実際に押印した日付を契約締結日とするケースです。
会社によっては押印するルールや運用は様々ですので、具体的な日付は先に署名する側のルールや運用など社内事情によって決まってしまう事になります。その点において、後か署名する側としては納得しにくい部分もありそうです。
方法③最後の当事者が契約書へ署名した日とする
方法の3番目は、2番目と逆のケースです。いわゆる、後から署名捺印する当事者が、実際に押印する日付を契約締結日とするケースです。
この場合、先の当事者は、作成した契約書の契約締結日欄を空白にしたまま、相手方へ郵送するのですが、一つ課題が残ります。
後の当事者によって契約締結日をいかようにも記入されてしまうというリスクです。契約行為における義務の履行期間が契約締結日と定められている場合などはトラブルにつながる可能性がございます。
また、後の当事者が記入を忘れてしまうというリスクもございます。忘れてしまう場合では、正式な契約締結日が空白のまま保管されてしまいますので、こちらもトラブルにつながる可能性がございます。
方法④基本的な条件に双方が合意した日とする
契約書を発行するタイミングにおいては双方が契約書に記載されている内容に対して合意されている事がほとんどです。そうであれば、その最終的な合意をした日付を契約締結日とする方法も考えられます。
各当事者の窓口となる担当者であれば、この合意をした日付というのは双方の確認の履歴から明確になるケースが多いでしょうから双方納得しやすいというメリットはあるかもしれません。
方法⑤すべての関係者の社内承認が完了した日とする
また契約書を発行するという事は、それよりも前に双方の社内で契約を締結する事への承認プロセスがあるかと思います。そこで、例えば、双方が契約書の基本事項に合意し社内ワークフローなどで決裁された日付を契約締結日として取り決めるという事もありえます。それぞれの当事者からの報告義務は必要とはなりますが、双方の当事者の然るべき承認者による手続きがあるという点においては、推奨されやすい方法とも言えます。
契約実務書では後押印日が一般的
契約書を取り交わすには当然のように当事者双方の署名捺印を求める事が多いです。
法的には、署名捺印が無くとも契約行為は有効となりますが、後々の法的証拠力としても署名捺印をされるのがほとんどでしょう。
上記の観点で言えば、契約書という書面の作成が完了するのは、双方の署名捺印を得た時点とも言えます。その為、契約実務書の中では後押印日を契約締結日とする考えを採用している文献もございます。
上述の方法③の中で、後押印日による決め方でのリスクについて触れました。リスクについて双方認識を合わせ、必要な対策を講じて後から押印した日付を契約締結日とするのは理にかなっているかもしれません。
契約締結日・効力発生日を変更したい場合

次に、混同されがちな契約の効力発生日と契約締結日の観点からご説明いたします。
契約締結日は、契約を実際に取り交わした日付と解釈します。
一方で、効力発生日は契約書に定められる権利や義務といった効力が開始される日付となります。
よって、契約締結日と契約の効力発生日は必ずしも一致しないのですが、この日付をそれぞれ別の日付にする方法については少し注意が必要となります。
効力発生日を「過去」に設定する方法
まず、過去の特定の日付から契約書の効力を発生させる為の方法についてご紹介いたします。
秘密保持契約を締結する場合などで、情報を公開した後に契約を締結し、公開した日付に遡って効力を発生させるというケースなどです。契約の遡及適用、遡及契約といわれます。
具体的な方法としては、契約書へ以下のような記載をします。
(例)「本契約は、契約締結日に関わらず、〇〇〇〇年〇月〇〇日より遡及的に効力を有するものとする。」
このような一文で、契約の効力発生日を過去から適用する事ができます。そしてこの記述によって持たせる効力の事を「遡及効」と呼びます。
効力発生日を「未来」に設定する方法
上記とは逆のケースです。実際の契約における取引の開始前に契約を締結しておくという事もございます。
あらかじめ締結しておく秘密保持契約書などが想定されます。このような場合も、契約書の条項の中で契約の効力発生に関する取り決めを記載しておくようにしましょう。
具体的な方法としては以下のような記載をします。
(例)「本契約の効力発生日は〇〇〇〇年〇月〇〇日とする。」
契約締結日を定める際の注意点

契約の効力発生日について触れました。
それでは話を契約締結日に戻し、契約締結日における注意点についてご紹介いたします。
契約締結日のバックデートはしない
契約の効力発生日においては、過去に遡った日付から効力を持たせる方法をご紹介しましたが、契約締結日ではバックデートはしないようにしましょう。
締結した日付より過去には、その契約はそもそも存在はしなかったはずです。そうであるにも関わらず、契約締結日を遡って記載する事は、契約書そのものが虚偽のものともいえてしまいますし、何より企業におけるコンプライアンス管理の点でも大きな問題になるかと思います。
先ほどご紹介しました遡及契約の記載事例を参照いただき、契約締結日については実態に合わせた日付で記載するようにしていただければと思います。
契約締結日の記載漏れ
ありがちなケースが契約締結日の記載漏れです。
どちらが、どのような日付を契約締結日とするのか曖昧なまま進める場合に起こりがちな事例です。
双方の署名捺印や記名押印がされた契約書に、後から日付を自由に記載できるのは相当なリスクがある事を認識いただければと思います。
記載漏れがないようにする為には、先にご紹介しました契約締結日を決める方法について、双方で取り決めておき、その方法に従った日付を記載するという事を徹底していくようにしましょう。
まとめ
以前にも契約締結日に関するコラムをご紹介しておりましたので、内容としては重複している部分もございます。
しかしながら、契約書における日付の概念はとても重要な役割を果たしております。
契約書の性質として、双方の権利と義務についてまとめているものであるという点がございます。
しかし、その権利と義務が有効と言えるのは契約に定められる日付があってこそです。
日付を間違える、記入漏れのまま保管してしまう、という事がないように改めて注意するようにして頂ければと思います。
また電子契約であれば、日付という概念をタイムスタンプによって管理する事もできますので導入をご検討されたいという方は下記より無料の資料をダウンロードください。